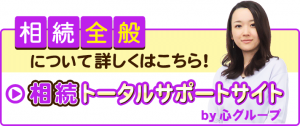相続税の農地の納税猶予
みなさんこんにちは!
名古屋も朝夕はだいぶ涼しくなってきました。
ただ、日中は相変わらず暑いので、熱中症にはお気を付けください。
さて、本日は、「相続税の農地の納税猶予」についてお話していこうと思います。
まず、農地の納税猶予の特例とは、簡単にいうと、農地を相続した相続人が引き続き農業を営む場合等には、相続税の計算上、農地を通常の相続税評価額よりも低い金額で評価し、それを超える価額に対応する相続税については納税を猶予するという制度のことを言います。
また、農地を相続した相続人が亡くなった場合等では、猶予された相続税は免除されることになります。
そのため、農地について代々、農業を相続人が継続して行っていく場合は、相続税は、その分安くなるというのがこの制度の内容です(詳細については、以下の国税庁のホームページも参照ください。国税庁:農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例)。
たとえば、遺産として、農地とその他の財産(預貯金や自宅土地建物)があり、農地の相続税評価額が1億円(農業投資価格300万円)、その他の財産の価額が1億円の場合、納税猶予の特例を使わない場合は、農地について1億円を基準に相続税が計算されることになり、相続人が子1人の場合、相続税額は、4860万円となります。
他方、納税猶予の特例を使った場合、農地の評価額を農業投資価額の300万円で評価することになり、相続税額は、1310万円となります。
そのため、農地の納税猶予を使うか否かで、3550万円もの相続税に差が生じることになります。
このように、農地の納税猶予については、適用の有無で大きく相続税が異なる場合があるため、農地をお持ちの方は、適用について検討しておいた方が良い特例ではあります。
もっとも、農地の納税猶予については、いくつかの落とし穴や注意点があります。
まず、農地の納税猶予の特例については、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまっている必要があり、相続人間で遺産の配分について揉めている場合で申告期限に間に合わない場合、この特例を使うことはできません。
この点は、小規模宅地等の特例とは異なりますので、注意が必要です。
また、農地の納税猶予の特例については、相続税の申告期限から3年ごとに継続届出書というものを税務署に提出する必要があり、これを忘れてしまうと、納税猶予が取り消されることになります。
他にも、農地を相続した相続人が農業を途中でやめてしまった場合や、一部の農地を売却してしまった場合や耕作を放棄してしまった場合などは、納税猶予が取り消される可能性があります。
仮に納税猶予が取り消されてしまった場合、猶予されていた相続税を追加で納めるだけでなく、それまでの利子税(利息のようなもの)も追加で納める必要があります。
このように、農地の納税猶予については、相続税を大幅に猶予できるというメリットもありますが、いろいろな注意点や落とし穴もあるため、適用を検討される際は、事前に相続税に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、今回に関連して、「農地の相続税評価額」についてお話していこうと思います。
それではまた!
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒453-0015愛知県名古屋市中村区
椿町14-13
ウエストポイント7F
0120-41-2403