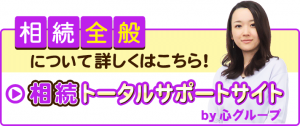複数の遺言がある場合の遺言の効果
みなさんこんにちは!
名古屋も急に熱くなってきましたので、熱中症などにはお気を付けください。
さて、本日は、「複数の遺言がある場合の遺言の効果」について、お話していこうと思います。
まず、基本的に、最新の遺言(作成日が新しい遺言)が基本的に有効であり、作成日が古い遺言については、作成日が新しい遺言と矛盾する部分について無効になります。
たとえば、令和7年3月1日作成の遺言(旧遺言)に
「①自宅不動産は、長男に相続させる。
②預貯金は長女に相続させる。
③株式は、次男に相続させる。」
という文言があったとします(なお、他の遺言作成の要件はすべて問題ないとします。)。
その後、令和7年5月1日作成の遺言(新遺言)には、
「預貯金及び株式を長男に相続させる。」
という文言があったとします。
この場合、
①自宅不動産については、令和7年3月1日の遺言(旧遺言)と令和7年5月1日の遺言(新遺言)は矛盾しない(そもそも記載がない)ため、令和7年3月1日の遺言(旧遺言)の①の文言の効力は変わりません。
他方、②預貯金と③株式については、両者の遺言が矛盾するため、令和7年3月1日の遺言(旧遺言)が無効になり、令和7年5月1日の遺言(新遺言)が有効になります。
ここで応用として、A遺言があり、その後、A遺言と矛盾するB遺言が作成され、さらにその後、B遺言と矛盾するC遺言が作成された場合はどうなるのでしょうか。
遺言を作成する方(遺言作成者)が高齢な場合、周りの親族に流されて親族の一方に有利な遺言を作成してしまうことがあり、それに気づいたほかの親族がさらに遺言作成者を誘導し、自身に有利な遺言を作成させる結果、このような遺言が作成されることがあります。
この場合、一番新しいC遺言の効果が有効になります。
ここで注意点として、C遺言作成時において、遺言作成者が認知症などにより正常な判断が困難な場合やC遺言が遺言書の作成条件を満たしていない場合、C遺言が無効になる場合があり、C遺言が無効になった場合は、B遺言が有効となります。
そのため、遺言は基本的に新しいものが有効ですが、新しい遺言が無効な場合は、その前の遺言が有効になります。
さて、次回は、「偽造、変造された遺言の効果」についてお話します。
それではまた!
月別アーカイブ
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒453-0015愛知県名古屋市中村区
椿町14-13
ウエストポイント7F
0120-41-2403